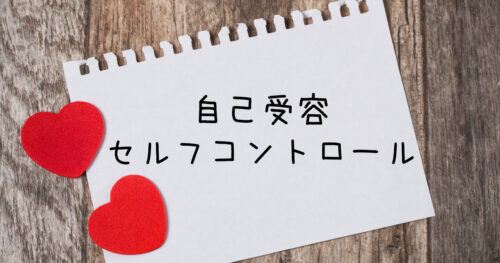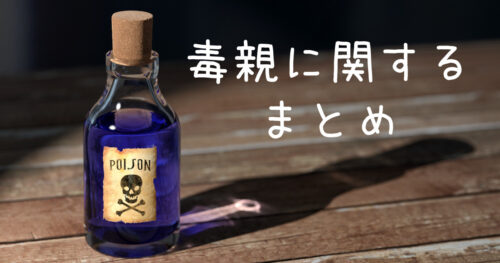投稿日:2025年4月18日 | 最終更新日:2025年4月18日
最近では「HSP(繊細な人)」という言葉が広まり、 「もしかして私もHSPかもしれない」と感じる人が増えてきました。
実際にHSP気質を持っている方はたくさんいますが、 その中には、HSS型HSPという「刺激を求める一方で繊細な自分に疲れるタイプ」がいます。
一方で、HSP×ADHDという「感受性が強く、かつ思考や感情が散らばりやすいタイプ」も存在します。
この二つの気質はとても似ており、しかし決定的に違う部分もあります。
今回は、HSS型HSPである私自身の経験をもとに、 「似ているようで、まったく違うこの2つのタイプ」について、 実際の関わりの中で感じた違和感や違いを言語化していきます。
HSS型HSPとは?その特徴と日常での傾向
HSS型HSPとは、「刺激を求める気質(High Sensation Seeking)」と、「繊細な気質(HSP)」が合わさったタイプです。
このタイプの人は、
- 新しい体験や人との出会いにワクワクする
- だけど刺激にすぐ疲れる
- 一人の時間が必要不可欠
- 感情の起伏はあるが、他者に迷惑をかけないようコントロールする
という「矛盾」を抱えて生きています。
会話における特徴
HSS型HSPは、テンション高く話すことがあっても、 相手のテンポや空気に合わせる配慮が自然とできることが多いです。
「私はこう思うけど、相手にはどう伝わるか」 という“受け手視点”が常に頭にあるため、話しすぎてしまった時にも自覚があります。
境界線の感覚について
HSS型HSPの大きな特徴のひとつが「境界線を引ける力」です。
共感力は非常に高いのですが、相手の感情を自分の中に入り込ませすぎず、 「これは相手の問題、これは自分の課題」と区別する意識があります。
また、自分のエネルギーが減ってきたときや、 人との関係性に違和感を覚えたとき、 そっと距離を置いたり、内省によって調整したりすることが自然にできます。
HSP×ADHDという可能性

一方で、「自分はHSS型HSPだと思っていたけど、なんだかしっくりこない…」 という方の中には、ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持っている場合もあります。
HSP×ADHDの人は、
- 外部からの刺激に敏感(HSP)
- だけど思考がまとまりにくく、話題が飛びやすい(ADHD)
- 衝動的に発言したり、感情が爆発しやすい(ADHD)
- 長文になりがちで、要点が伝わりにくい(ADHD)
という特性をあわせ持つことがあります。
境界線の曖昧さ
HSP×ADHDの人は、共感性が高いというよりも、 「他人の感情に過剰に反応してしまい、自分と他人の境界が曖昧になる」傾向があります。
- 相手に合わせすぎて疲れる
- でも断ったり距離を取ると罪悪感や不安になる
- 感情に飲み込まれた結果、ヒステリックな爆発や極端な落ち込みにつながる
ADHDの気質を併せ持つと、感情に飲み込まれた結果、ヒステリックな爆発や極端な落ち込みや自己否定につながることがあります。
そのときは夢中で反応していても、あとから「どうしてあんなに感情的になったんだろう」と自分でもモヤモヤすることがあるかもしれません。
境界線を意識する以前に、「どこまでが自分の感情か」が見えにくい状態です。
HSS型HSPとHSP×ADHDの違い(比較表)
HSS型HSPとHSP×ADHDの違いを比較してみると、以下のようになります。
| 特徴 | HSS型HSP | HSP×ADHD |
|---|---|---|
| 話し方 | テンポは速めでも相手に配慮 | 早口で話が飛び、整理されない |
| 会話のリズム | 相手の反応を見て調整できる | 自分の思考のまま話す |
| 感情コントロール | 基本的に抑制的 | 感情が爆発・過敏になることも多い |
| LINEなどの文章 | まとまっていて整理されている | 長文で支離滅裂になりやすい |
| 境界線の感覚 | 自他を冷静に切り分けられる | 境界線が曖昧で混乱しやすい |
HSPの自己理解に、こちらの目線もご参考ください。
実際にあった「違和感」のエピソード

以前、ある人との関係の中で、「あ、この人もHSPなんだな」と思って関わっていたのですが、 なぜか毎回すごく消耗するという感覚がありました。
話すテンポがとても速くて、会話のキャッチボールというより、情報の一方通行になりやすい。
LINEは長く、伝えたいことが読み取りづらい。
そして、私が少し落ち着いたトーンで返信をしたとき、驚くほど傷ついた反応が返ってきたこともありました。
「なんでこんなに疲れるんだろう?」と考えると、相手の繊細さや共感力そのものというより、感情や情報をうまく整理できないところに、すれ違いの原因があるのかもしれないと感じました。
HSPタイプを見極めることが大切な理由

HSPやHSS型HSPといった言葉は、自分を知るヒントにはなりますが、 「自分はHSPだから仕方ない」と思い込んでしまうと、 適切な対処法を見逃してしまう可能性があります。
対処法が異なる例
- HSS型HSP:予定を詰めすぎず、一人時間を確保することで回復
- HSP×ADHD:タスク整理や会話の構造化など、脳の特性に合った工夫が必要
どちらも「繊細」であることに違いはありませんが、 「繊細さの質」が違えば、必要なケアも違うのです。
境界線の感覚の違い
また、境界線の感覚の違いは、気質の差としてある程度、定義づけることができます。
- HSS型HSP:共感力が高くても「これは相手の感情、これは自分の感情」と切り分けることができ、内省や自己調整によって距離感を保ちやすい
- HSP×ADHD:相手の感情を強く受け取りすぎてしまい、自分の感情と混ざってしまうことで、どこまでが自分かわからなくなり、境界線が曖昧になりやすい
この違いを理解しておくことで、人との距離感や関わり方において、 「なぜ疲れるのか」「なぜ通じないのか」に納得がいく場面が増えます。
まとめ:自分の繊細さの「質」を知ることで、楽になれる
「この人とは気が合うと思っていたのに、なんだか疲れる」
「優しくしているはずなのに、すれ違ってばかり」
そんなときは、相手の気質や特性が、自分と少し違うのかもしれません。
どちらが良い・悪いではなく、「違うだけ」。
その「違い」を理解しておくことが、 人間関係の中で自分をすり減らさないひとつの方法になります。
そして何より、 「繊細さ」は適切に扱えば「強さ」にもなります。
あなたの敏感さが、あなた自身と周囲を守る力になりますように。